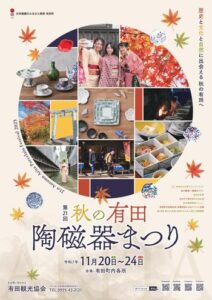有田町磁器産業の立役者 英(はなぶさ)山
有田は日本の磁器産業誕生の地として知られています。有田の歴史は17世紀初め、泉山で陶石が発見されたことに始まります。
泉山の陶石は、磁器製品を作るのに必要な成分を有する理想的な陶石です。

言い換えると、磁器製品を製造するのに他の成分と調合の必要がなく、泉山のような単体で磁器製品を製造できる陶石は世界で二か所しかありません。
どちらも日本国内にありますが、泉山は最初に発見されました。
かくして泉山は有田の街と日本の磁器産業を生むことになるのです。
さて、投稿の右側写真にあるのは、泉山の近くにある山です。
その名は、英山。
何の変哲もない山ですが、この英山こそが泉山を理想の陶石の山に仕立てた立役者なのです。
以下がその顛末です。


約250万年前、泉山に地殻を溶かしながらあがってきたマグマが冷えて流紋岩と化しました。
流紋岩の垂直の貫入を通って300度の熱水もあがってきました。 ⇒ マグマの通り道や貫入時にできた割れ目を通って300度の熱水もあがってきました。
そこで登場したのが英山。
英山が噴火したのです。 そしてその流れ出た溶岩は泉山をすっぽりと鍋の蓋のように覆ったのです。
蓋の中では流紋岩と熱水が数万年もの間ぐつぐつと煮え、やがて流紋岩は白く洗われて理想的な陶石となりました。
つまり英山なくしては泉山は磁石場にはなり得なかったのです。

ひいては、有田の街は生まれず、日本の磁器産業の誕生も遅れたことでしょう。 これ故、英山は有田と日本の磁器産業誕生の立役者だと言えるのです。
(K.H.)