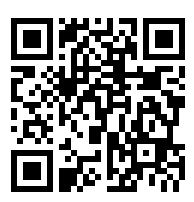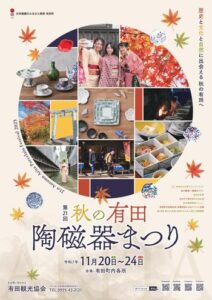有田焼、その色絵(赤絵)と歴史
有田焼は、器の色付けの方法において、2つの種類に大別することができます。一つは、「染付」です。白い器の上に藍色が施されています。カジュアルにブルー&ホワイトと呼ばれることもあります。
そしてもう一つは、色絵と呼ばれる種類です。伝統的な表現で、赤絵と呼ばれることもあります。こちらには、藍色ばかりでなく、赤や黄や緑など鮮やかな色が施されています。
有田町の中心領域に「赤絵町」という地区があります。「Akae」とは赤い色付けのことです。それは、中国の色絵に基づいて、有田町で17世紀半ばに開発された技法です。
当時の君主が技法の秘密を保つために、一定地区に赤絵の絵付師を集中させたのです。それが赤絵町の由来です。


それでは、なぜ秘密を保たねばならなかったのか。その理由は、有田焼の行政的管理者である佐賀藩鍋島家が将軍や大名への献上品として、赤絵を差別化する必要があったからです。佐賀藩とは現在の佐賀県とほぼ同様の行政単位です。将軍は、すべての藩の統治者、大名は、藩の管理者を意味します。鍋島家とは藩を管理する家名のことです。
そのような経緯から、鍋島家が管理する窯を鍋島藩窯と呼び、献上品としての生産物を色鍋島とか鍋島焼などと称しています。Hanyouとは鍋島藩専用の窯という意味です。現在の赤絵町には、これらの歴史の足跡を残すスポットがあります。人間国宝である第14代、今泉今右衛門さんの創作工房「今右衛門窯」です。
二階の窓の下の屋根瓦に赤い色が染みついています。これは絵付師が、創作後に残った絵具を、二階の絵付け場から捨てた名残とされています。電気の灯りがなかった当時は、窓のそばで絵付け作業をおこなっていたことも分かります。

現在でも、窓のそばで絵付けをしている様子を見学することができます。今右衛門窯から北西部、車で10分以内の地区に「源右衛門窯」の作業場があります。ここでは成形から施釉、濃み、絵付けに至るプロセスを見ることができ、撮影も基本的に自由です。
有田町の色絵・赤絵について、伝統的作業を確認するのに、源右衛門窯はおススメのスポットです。(T.S.)